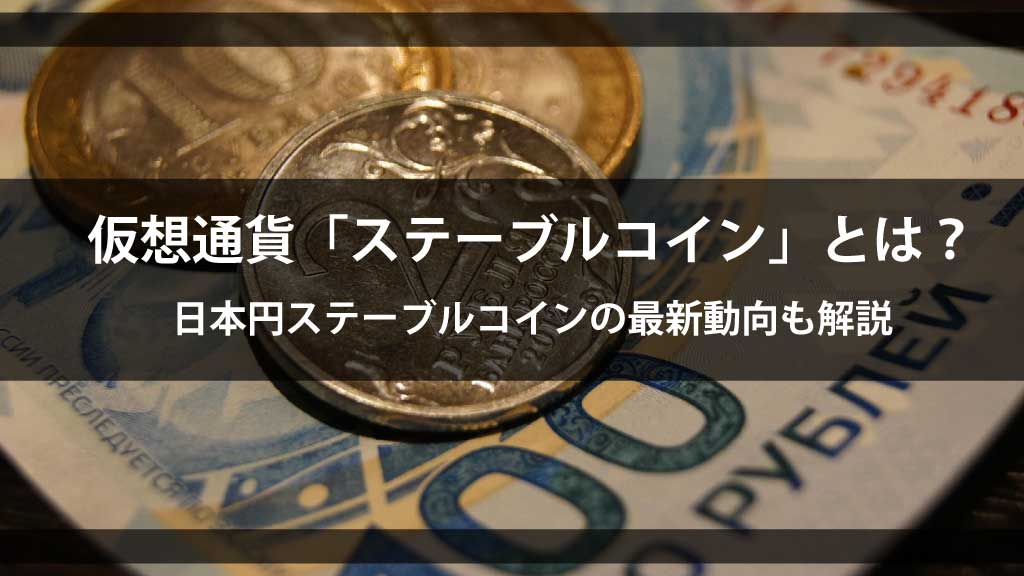仮想通貨の「安定版」として注目されるステーブルコイン
ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨は価格変動が激しい一方、安定した価値を持つことを目的に設計されたのがステーブルコイン(Stablecoin)です。本記事では、仕組み・種類・活用事例・リスク、そして日本円ステーブルコインの最新動向までをわかりやすく解説します。
ステーブルコインとは?
ステーブルコインは、法定通貨(日本円・米ドルなど)や資産(ゴールドなど)に価値を連動させ、価格の安定を目指す暗号資産です。一般的な暗号資産のような急激な値動きを抑え、決済・送金・DeFiなどでの使い勝手を高めます。
主な目的
- 決済・送金の安定性とコスト削減
- 相場急変時の資金退避(ボラティリティ回避)
- DeFiでの担保・基軸通貨としての活用
ステーブルコインの種類
(1)法定通貨担保型(Fiat-collateralized)
発行体が法定通貨(例:米ドル)などの準備金を保有し、その裏付けでコインを発行。代表例は USDT(Tether)、USDC(USD Coin) など。
特長:安定性が高い一方、発行体の管理・透明性に信頼が依存します。
(2)仮想通貨担保型(Crypto-collateralized)
担保にETHなどの暗号資産を用い、価格変動に備えて過剰担保(例:150%)を要求。代表例は DAI(MakerDAO)。
特長:分散性が高いが、担保資産のボラティリティリスクは残ります。
(3)無担保・アルゴリズム型(Algorithmic)
担保を持たず、供給量調整などのアルゴリズムで価格維持を試みるタイプ。理論的には分散的ですが、実運用の安定性は低く、過去には崩壊事例もあります。
ステーブルコインの活用シーン・メリット・リスクと課題
主な活用シーン
- 取引の中間資産:相場急変時に一旦退避
- 国際送金・決済:高速・低コストでの価値移転
- DeFi運用:レンディング、流動性提供、イールド獲得
- EC・サービス決済:一部企業が導入を拡大
さらに近年では、グローバルなWeb3プロジェクトやブロックチェーンゲーム内での基軸通貨としてステーブルコインの採用が広がっています。価格変動が少ないため、国境を越えたマイクロペイメントや報酬配布にも最適とされています。
メリット
- 価格の安定性が高く、会計・決済実務に馴染みやすい
- 法定通貨と暗号資産の橋渡し(オンチェーン経済の基盤)
- 送金・決済コストの削減と処理の迅速化
- DeFi・NFT・Web3全般でのユースケースが広い
また、ステーブルコインを活用することで、企業がグローバル決済インフラを自社で構築できる点も大きな利点です。銀行ネットワークを介さずに24時間即時決済が可能となり、特に海外取引や越境ECにおいてコストと時間を大幅に削減できます。
リスクと課題
- 発行体リスク:準備金の透明性、監査体制への依存
- 規制リスク:各国で法整備が進行中、要件の変更可能性
- システムリスク:アルゴリズム型の破綻・市場心理の影響
- 流動性リスク:大量償還・引き出し時の対応能力
さらに、地政学的リスクや国際制裁などにより、特定通貨建てステーブルコインが利用制限を受けるケースも想定されます。特に米ドル建てコインでは規制当局の動向が取引環境に直接影響するため、利用者は法域ごとのリスクも把握しておく必要があります。安定を謳う資産でもゼロリスクではない点に留意。信頼できる発行体・仕組みかを見極めることが重要です。
日本における制度・代表例と最新動向
日本では2023年以降、関連制度の整備が進み、銀行や資金移動業者などが一定の枠組みでステーブルコイン相当の仕組みを提供できる環境が整いつつあります。これにより、日本円連動型の活用拡大が見込まれます。
JPYC(日本暗号資産市場株式会社)
1円=1JPYCを目安に発行される、前払い式支払手段に分類されるトークン。銀行口座連動の「預り金型」ではないものの、日本円建てで安定した取引が可能で、決済やオンチェーン利用が進んでいます。
- 口座不要で発行・利用が可能
- 複数チェーン対応(例:Ethereum/Polygon 等)
- 企業・自治体との実証実験や地域通貨連携が活発
Progmat Coin(三菱UFJ信託銀行)
信託スキームを用いた「信託型ステーブルコイン」構想。法定通貨を信託財産として裏付けに持ち、1円単位の安定移転を目指します。金融機関・企業間の資金決済や、将来的な国際送金・デジタル証券決済との連携も視野。
- 法的裏付け・ガバナンスが強く、信頼性が高い
- 法人決済・インフラ用途に適性
- 国内Web3基盤との相互運用性に期待
そのほかの動き
- SBIグループによる円連動ステーブルコイン構想(例:Scoin など)
- GMO-Z.com Trust Company のGYEN
- 地方銀行や地域事業者と連携したデジタル地域通貨プロジェクト
これらは国内決済の効率化やWeb3インフラ整備に直結し、2025年以降は「円建てデジタルマネーの統合基盤」としての役割拡大が見込まれます。
ステーブルコインとSWIFTの関係
結論から言うと、ステーブルコインとSWIFTには「直接的な関係はない」が、金融インフラとして“競合・補完”の両面関係にあるといえます。以下でわかりやすく整理します。
両者の基本的な位置づけ
| 項目 | ステーブルコイン | SWIFT |
|---|---|---|
| 主体 | 民間のブロックチェーンネットワークや発行体(例:Tether、Circle、MUFGなど) | 国際銀行間通信協会(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) |
| 仕組み | ブロックチェーン上での価値移転(トークン送信) | 銀行間で送金指示メッセージ(MT・ISO20022形式)を送受信 |
| 主な目的 | 即時・低コストな資金移転、決済 | 国際送金・貿易決済・銀行ネットワーク連携 |
| 実際の資金移動 | オンチェーンで即時完了 | 各国の銀行勘定経由で数日要する場合あり |
要するにSWIFTは「メッセージの送信網」、ステーブルコインは「実際に価値が動くネットワーク」です。同じ“国際送金”を扱いますが、アプローチがまったく異なります。
補完関係の側面
最近では、ステーブルコインやCBDCを既存のSWIFTネットワークに接続する実証実験も行われています。たとえば、
- SWIFT + Chainlink 実験(2023)
→ 異なるブロックチェーン間でのステーブルコイン/CBDC送金を、SWIFT経由で指示・橋渡しする試み。
→ 各国中央銀行デジタル通貨(CBDC)を共通ネットワークで動かす目的。 - MUFG Progmat Coin × SWIFT連携構想(国内議論)
→ 将来的には、企業間決済で「円建てステーブルコイン決済」と「SWIFT国際送金」を連携させ、即時かつ法的に裏付けのある国際決済を実現する構想も。
つまり、SWIFTがステーブルコインの“送信経路”として機能する可能性が出てきています。
競合関係の側面
一方で、ステーブルコインはSWIFTのビジネスモデルに対する「分散型の挑戦者」でもあります。
- ステーブルコイン(例:USDC)は、オンチェーンで即時決済が可能。
- 手数料が数十円〜数百円と安価(SWIFT送金は数千円以上かかることも)。
- 個人や企業が銀行を介さずに国際送金できる。
そのため、特に新興国では「SWIFTを使わずにUSDTで海外送金」する動きがすでに拡大しています(例:アフリカ・中南米の送金市場)。
今後の展望
- 短期的には共存関係:
銀行・大企業はSWIFTを基盤としつつ、ステーブルコインを補助的な決済レイヤーとして採用。 - 中長期的には融合の可能性:
SWIFTがブロックチェーン間メッセージングの標準化を進めており、将来的には「SWIFT経由でステーブルコインを送る」時代が来る可能性があります。
ステーブルコインとSWIFTのまとめ
| 観点 | 現状 | 将来像 |
|---|---|---|
| 技術的関係 | 直接的な結合はなし | ブリッジ/連携実験が進行中 |
| 立ち位置 | ステーブルコイン=資金移転の“新経路” | SWIFT=銀行間メッセージの“共通言語” |
| 関係性 | 競合でもあり、補完的でもある | 統合的な国際金融インフラへ発展する可能性あり |
よくある質問(FAQ)
Q1. ステーブルコインは本当に価格が動かないの?
A. 完全に固定ではありません。ペッグ(連動)を目指す設計ですが、市場環境や発行体要因で一時的に乖離する場合があります。
Q2. どの種類が一番安全?
A. 一概に断定はできません。多くの場合、法定通貨担保型は値動きが小さい傾向にありますが、準備金の透明性や監査を必ず確認しましょう。
Q3. 日本円ステーブルコインはどこで使える?
A. プロジェクトにより異なります。オンチェーン決済、EC、法人間決済、地域通貨連携など、利用先は拡大中です。
Q4. ステーブルコインに利息はつくの?
A. 一般的なステーブルコイン自体に利息はつきませんが、DeFi(分散型金融)プラットフォームに預けることで利回りを得られる場合があります。ただし、プラットフォームごとのリスク(ハッキング・契約不備など)を十分に理解して利用しましょう。
Q5. ステーブルコインを使った送金に税金はかかる?
A. ステーブルコインを「送金」や「支払い」に使うだけでは原則として課税対象になりませんが、売買や交換による利益が発生した場合は課税の可能性があります。特に海外送金・仮想通貨交換を伴う場合は、税務上の扱いを事前に確認しておくと安心です。
Q6. 企業が自社でステーブルコインを発行できるの?
A. 日本では、2023年に施行された改正資金決済法により、銀行・資金移動業者・信託会社など一定のライセンスを持つ事業者が、ステーブルコインを発行できるようになりました。一般企業が独自に「法定通貨連動トークン」を発行する場合は、これらの事業者と連携して発行スキームを構築するのが一般的です。
たとえば三菱UFJ信託銀行の「Progmat Coin」では、企業が自社ブランドでコインを発行し、同社が信託機能を担う構成が採用されています。
Q7. JPYCと電子マネーは何が違うの?
A. JPYCはブロックチェーン上で発行される前払い式支払手段であり、SuicaやPayPayのような電子マネーとは法的な位置づけが異なります。電子マネーは通常、特定の事業者内部でのみ利用できますが、JPYCはオープンなブロックチェーン上で他社間・他サービス間でも自由に移転可能です。ただし、JPYCは「預金」ではないため、破綻時に預金保険のような保護は受けられません。
Q8. ステーブルコインが破綻したら、償還されるの?
A. 発行体の種類や管理方法によります。法定通貨担保型であれば、通常は発行体が保有する準備金をもとにユーザーが償還請求できますが、監査体制が不十分な場合や資産凍結が起きた場合は、全額返金されないリスクもあります。
アルゴリズム型の場合は担保が存在しないため、価格維持が崩れると回復は困難です。そのため、償還ルールや監査報告書を事前に確認し、信頼できる発行体を選ぶことが重要です。
ステーブルコインのまとめ

ステーブルコインは、オンチェーン経済に「価格の安定」をもたらす基盤資産です。日本でも制度整備が進み、JPYCやProgmat Coinなどの円建てソリューションが加速。今後は、日常決済・企業間決済・デジタル証券まで活用が広がる見通しです。一方で、発行体の信頼性・準備金の透明性・規制適合性の見極めは不可欠です。