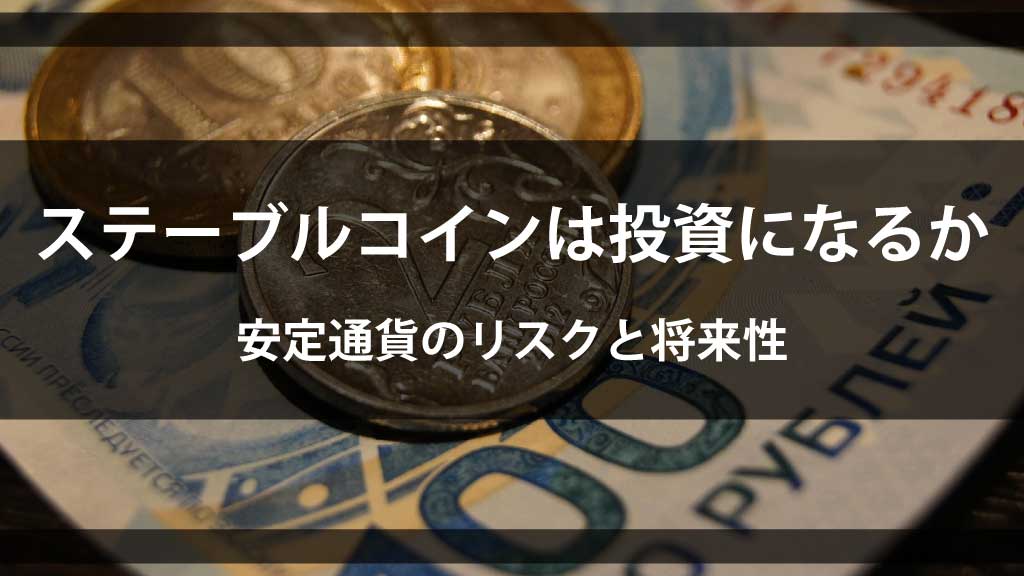ステーブルコインは投資の対象になりうるか?安定性と将来性を考察
ビットコインやイーサリアムが激しい値動きで注目を集める一方、「ステーブルコイン」は価格の安定性を売りにした暗号資産です。しかし、「安定している通貨に投資価値はあるのか?」という疑問を持つ人も多いでしょう。本記事では、ステーブルコインの仕組みとリスク、そして“投資対象になりうるか”を現時点での視点から考察します。
投資としての「定義」そのものを問い直す
そもそも“投資”とは「将来の価値上昇を見込んで資金を投じる行為」を指します。しかし、ステーブルコインは意図的に価格変動を排除しているため、従来の投資概念とはズレがあります。このズレをどう解釈するかが、ステーブルコインを投資として捉える第一のポイントとなります。
ステーブルコインの基本構造と分類
ステーブルコインは、価格を一定に保つために「裏付け資産」を持つ仕組みです。主に以下の3種類に分類されます。
| 種類 | 価格安定の仕組み | 代表例 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 法定通貨担保型 | 米ドルや円などの現金・国債で担保 | USDT、USDC | 信頼性が高いが、中央集権的 |
| 暗号資産担保型 | ETHなど他の暗号資産を超過担保 | DAI | 分散性が高いが、市場変動に影響されやすい |
| 無担保(アルゴリズム型) | 供給量を自動調整して価格を維持 | FRAX(旧USTなど) | リスクが高く、破綻例もある |
担保の「透明性」と「流動性」の違いに注目
同じ「1ドル担保型」であっても、裏付けとなる資産の性質によって安全性が大きく異なります。現金や短期国債を保有しているUSDCは高流動ですが、一方でUSDTは商業手形など換金性の低い資産を多く含むと指摘されています。投資の安全性を測るには、「何で担保されているか」ではなく「すぐ現金化できるか」を見るべきでしょう。
ステーブルコインの「安定」は本当に安全か
- 発行体の信用リスク:準備資産の保全・分別管理・監査体制に依存。
- 規制リスク:各国の金融当局による監視・制限の強化。
- ペッグ崩壊リスク:特にアルゴリズム型は急激な需給変化に弱い。
「安定=ゼロリスク」ではない現実
価格が安定して見えるのは、市場が信頼を保っている間だけです。2022年のUST崩壊は、市場参加者に大きな教訓を残しました。ステーブルコインは「安定通貨」というより、信頼通貨(トラストコイン)と呼ぶべき存在かもしれません。
実例:USDC運用に見る「安定通貨投資」のリアル
2024年以降、USDCを用いた短期運用は企業・個人を問わず広がりを見せています。たとえば、米国の中小輸出業者が売上代金を一時的にUSDCで保有し、CircleやCoinbaseが提供する利息付き口座に預けるケースがあります。この場合、年利2〜4%程度の利回りを得ながら、為替変動や銀行送金遅延のリスクを回避できます。
一方で、2023年3月のシリコンバレーバンク破綻時には、USDCの担保資産の一部が同行に預けられていたことが判明し、一時的に1USDC=0.88ドルまで下落しました。この経験は、「安定資産であってもバックにある実態を確認しなければならない」という教訓を残しました。
投資としての観点:値上がり益は期待できるか?
ステーブルコインは1ドル=1USDTのように価格を一定に保つため、値上がり益を狙う投資対象ではありません。しかし、次のような「間接的な投資機会」は存在します。
- ステーブルコイン預け入れによる利息収入(レンディング)
- 裁定取引(アービトラージ)
- リスク回避資産としての利用(避難・待機資金)
DeFi利回りの実態と「見えないリスク」
DeFi上の利息収入は高利回りになることもありますが、その背後では流動性提供リスク・スマートコントラクトの脆弱性・カウンターパーティリスクが存在します。伝統金融と違い「保証されていない」世界である点を忘れてはいけません。つまり、ステーブルコインの利回り投資は「信用リスクを取る代わりに金利を得る」構造といえます。
ステーブルコイン市場の拡大と今後の展望
2024〜2025年にかけて、ステーブルコインの発行残高は世界で2000億ドル規模に到達しています。今後は以下の方向で発展が予想されます。
- 各国中央銀行によるCBDC(中央銀行デジタル通貨)との共存・競合
- 決済・貿易・給与支払いなど実需ベースの利用拡大
- 金利付きステーブルコインの登場と普及
「金融インフラ」としての役割拡大
近年では、ステーブルコインがブロックチェーン上の決済レイヤーとして機能し始めています。大手決済ネットワークやフィンテック企業による採用が進み、単なる暗号資産ではなく、新しい金融インフラの中核になりつつあります。
図解:暗号資産市場におけるステーブルコインの位置づけ
安定性を活かして資金フローを調整する“戦略ツール”として
┌───────────────────────────
│ 高リスク・高リターン │ → ビットコイン・アルトコイン
└───────────────────────────
↓
┌───────────────────────────
│ 中間的役割:ステーブルコイン
│ 資金移動・保全・利息運用
└───────────────────────────
↓
┌───────────────────────────
│ 低リスク・低リターン │ → 現金・国債・CBDC
└───────────────────────────
まとめ:ステーブルコインは“投資”というより“戦略ツール”

結論として、ステーブルコインはビットコインのような投機対象ではなく、資産を守り、流動性を確保し、次の投資に備えるための中間資産と位置づけるのが現実的です。
“安定”を利用する者が利益を得る時代へ
市場が混乱する時こそ、安定を保つ資産の価値が高まります。今後は、ステーブルコインを単体で保有するのではなく、「投機資産との組み合わせ」や「自動運用戦略(DeFi戦略)」で、安定性そのものを活かす投資スタイルが主流になる可能性があります。