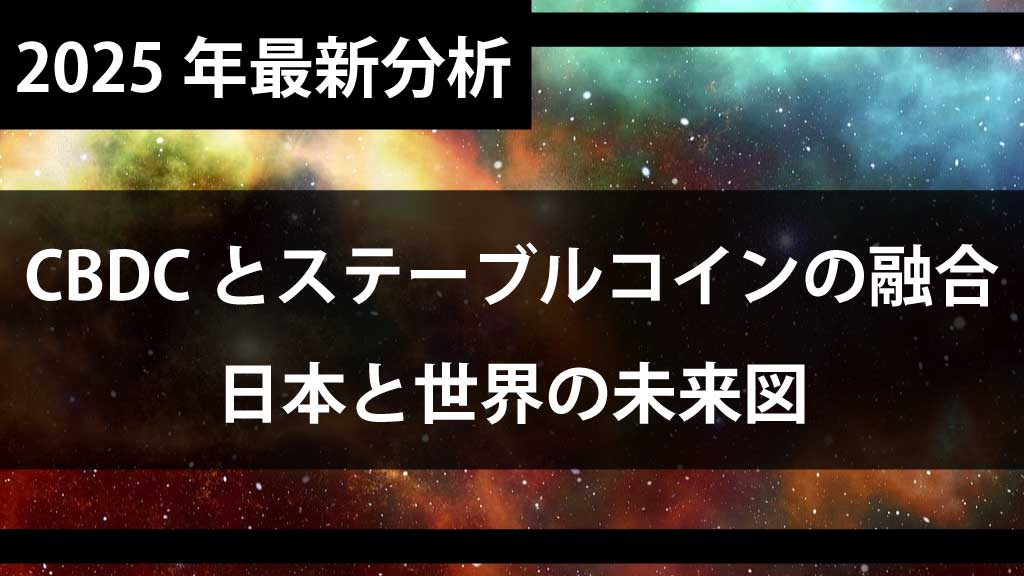はじめに|「二つのデジタル通貨」が交わり始めた時代
2025年現在、世界では二つの“デジタル通貨”が並行して進化しています。一つは、各国の中央銀行が発行を検討するCBDC(Central Bank Digital Currency:中央銀行デジタル通貨)。もう一つは、民間企業が発行するステーブルコイン(Stablecoin)です。
両者は目的も構造も異なりますが、共通しているのは「現金よりも速く、安全に、国境を越えて価値を動かす」という目標。この二つが競合から共存・融合の段階へと移行しつつあるのが、今の世界的潮流です。
CBDCとは何か|国家が発行する「デジタル法定通貨」

CBDC(Central Bank Digital Currency:中央銀行デジタル通貨)は、中央銀行が直接発行する電子的な法定通貨です。これまで現金(紙幣・硬貨)や預金を通じて間接的に流通していた通貨を、国家がデジタル形式で直接発行・管理する仕組みです。
つまり、CBDCは「現金のデジタル版」でありながら、「民間預金とは異なる、中央銀行への直接債権」を持つ点が最大の特徴です。この仕組みにより、国家が個人・企業レベルまで安全かつ即時に通貨を届けられるようになります。
なぜ各国がCBDCを発行しようとしているのか
CBDCの導入を後押しする要因は、単なる技術トレンドではなく、経済・金融政策・安全保障に関わる国家的課題にあります。
- ① 現金利用の減少: キャッシュレス化が進む中、国家が通貨流通を直接維持するため。
- ② 民間通貨の台頭: ステーブルコインや仮想通貨が広がる中で、国家通貨の信頼を補強するため。
- ③ 国際競争: 中国の「デジタル人民元」や欧州の「デジタルユーロ」に対抗する地政学的必要性。
- ④ 金融包摂: 銀行口座を持たない層へのアクセス拡大。
- ⑤ 政策実行性: 経済刺激策や給付金を直接かつ即時に配布可能にするため。
特に「通貨主権の確保」は重要なキーワードです。もし民間ステーブルコイン(例:USDT・USDC)が広く流通すれば、国家は自国経済における通貨発行権を一部失う可能性があります。CBDCはこのリスクに対する国家の“通貨インフラ防衛”という意味も持っています。
CBDCの二つのモデル|卸売型と小売型
CBDCには、大きく分けて「卸売型(Wholesale)」と「小売型(Retail)」の2つの設計モデルがあります。
| 区分 | 概要 | 主な利用者 | 想定利用目的 |
|---|---|---|---|
| 卸売型(Wholesale CBDC) | 銀行・証券会社など金融機関同士の取引で利用されるCBDC。 主に決済インフラの効率化を目的とする。 | 金融機関・中央銀行 | 銀行間送金・証券決済・RTGS(即時グロス決済) |
| 小売型(Retail CBDC) | 一般市民・企業が直接利用できるCBDC。 スマートフォンアプリ等を通じて日常決済にも対応。 | 個人・企業 | 小口決済・給付金支払い・消費促進政策 |
日本銀行は現在、小売型CBDC(デジタル円)のパイロット実証を進めており、2026年頃の制度設計を見据えています。一方、欧州や香港では、すでに卸売型CBDCの実取引テストが進行中です。
CBDCの技術的構造|中央集権と分散の融合
CBDCは、国家による中央管理の仕組みを保ちながらも、ブロックチェーン技術を部分的に採用する「ハイブリッド型アーキテクチャ」で設計されます。
主な技術要素は次の通りです。
- ① 中央台帳(Central Ledger): 中央銀行が全取引記録を保有・検証。
- ② 分散ノード構造: 商業銀行・決済事業者などが部分的に取引処理を分担。
- ③ API連携: 民間決済サービス(ステーブルコイン・電子マネー)との接続。
- ④ プライバシー保護: 個人情報を匿名化しつつ、AML/KYCを維持。
この構造により、CBDCは「銀行システムを完全に置き換える」のではなく、既存の決済ネットワークを拡張・統合する形で進化していきます。
CBDC導入の社会的インパクト
CBDCの発行は、単なる通貨のデジタル化にとどまらず、金融・経済・社会の仕組みを大きく変える可能性があります。
- 金融政策の即時性: 金利調整や給付を直接個人ウォレットへ実施可能。
- 取引データの可視化: 経済分析・税収把握がリアルタイム化。
- 現金経済の縮小: すべての資金移動がデジタル上で追跡可能に。
- プライバシー懸念: 政府が個人の支出データを把握するリスク。
- 通貨の越境化: CBDC同士の相互運用が可能になれば、国際送金革命へ。
つまり、CBDCは「国家の金融政策ツール」であると同時に、社会の透明化と管理の両刃の剣でもあります。利便性と個人の自由、その境界をどう設計するかが、今後の大きな課題といえるでしょう。
日本銀行の取り組み:デジタル円の実証フェーズ
日本銀行は、2023年から「パイロット実験」を段階的に実施しています。商業銀行・決済事業者が参加し、システム接続・オフライン決済・セキュリティ評価などを検証中です。2025年現在の実証段階は以下の通りです。
| フェーズ | 内容 | 期間 |
|---|---|---|
| 第1段階(概念実証) | 基本設計・技術検証 | 2021〜2022年 |
| 第2段階(実証実験) | 商業銀行連携・オフライン環境テスト | 2023〜2024年 |
| 第3段階(パイロット運用) | 民間連携・利用者テスト | 2025〜 |
デジタル円の正式発行時期は未定ですが、日銀は「民間との共存を前提とした設計」を強調しています。これは、Progmat Coinなど民間ステーブルコインとの共通基盤を見据えたものであり、次の章で解説する「融合」の前提となります。
ステーブルコインとは|民間が動かす「デジタルマネーの経済圏」
ステーブルコインは、民間企業や金融機関が発行する、法定通貨と価値を連動させた暗号資産です。担保構造や法的位置づけによって分類され、主に次の3タイプに分かれます。
- 法定通貨担保型: USDC・JPYCなど。銀行預金や国債を裏付け資産に。
- 暗号資産担保型: DAIなど。仮想通貨を担保に発行。
- アルゴリズム型: 発行量調整により価格維持(UST崩壊以降は縮小傾向)。
特に日本では、金融庁の認可を受けた「電子決済手段」としてのステーブルコイン(例:Progmat Coin、DCJPY)が商用化され、民間主導のデジタル通貨経済圏が形成されつつあります。
CBDCとステーブルコインの主な違い
| 項目 | CBDC | ステーブルコイン |
|---|---|---|
| 発行主体 | 中央銀行(国家) | 民間企業・金融機関 |
| 担保・裏付け | 国家信用による直接保証 | 法定通貨・国債・資産による間接保証 |
| 発行目的 | 金融安定・政策運営・決済効率化 | 取引利便性・国際決済・Web3経済対応 |
| 取引形態 | 中央集権型(国家管理) | 分散型(ブロックチェーン上) |
| 想定利用者 | 一般市民・金融機関 | 企業・個人・DeFi利用者 |
| 監査・透明性 | 国家会計による | 第三者監査・オンチェーン記録 |
両者は対立するものではなく、むしろ相互補完関係にあります。CBDCが「国家による信頼」を提供する一方で、ステーブルコインは「民間による技術とスピード」を担います。
日本の方向性|デジタル円と民間通貨の共存モデル
日本銀行は2025年に向けて「デジタル円パイロットプログラム」を開始し、商業銀行・決済事業者との連携を強化しています。同時に、民間では三菱UFJ信託のProgmat Coinや、デジタル通貨フォーラムのDCJPYが商用段階へと移行しました。
金融庁はこの動きを「公的通貨と民間通貨の並行実験」として位置づけ、次のような分担を示唆しています。
- CBDC:国内決済・公共支払い・金融政策ツール
- ステーブルコイン:企業間決済・国際送金・Web3経済圏での利用
つまり、日本は「中央集権と分散型の共存モデル」を世界に先駆けて模索しているのです。
世界の動向|主要国のCBDCとステーブルコイン戦略
| 国・地域 | CBDC状況 | ステーブルコイン対応 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 中国 | デジタル人民元(e-CNY)実証済・流通拡大中 | 民間発行は厳格規制 | CBDCを国家戦略として推進 |
| 欧州(ECB) | デジタルユーロ開発段階(2026年導入見込み) | MiCA規制でステーブルコインを統制下に | 国家と民間を法制度で共存化 |
| 米国 | CBDC検討中(連邦準備制度内で研究) | USDC・PYUSDなど民間発行が主流 | 民間競争型モデル |
| UAE・シンガポール | 国際CBDC実証(mBridge・Project Ubin) | ライセンス制度で民間コイン容認 | 国際取引重視のハイブリッド型 |
このように、世界各国では「国家管理型」「民間競争型」「共存型」の3モデルに分かれつつあります。日本はその中間に位置し、各国との連携実験(mBridge参加検討など)も視野に入れています。
融合の可能性|CBDC×ステーブルコインの相互運用構想
今後は、CBDCとステーブルコインが共通基盤でやり取りできる「相互運用(Interoperability)」が鍵になります。具体的には、次のような融合シナリオが想定されています。
- Progmat CoinやDCJPYが、日銀デジタル円APIと接続して即時精算
- 国際送金では、各国CBDC同士がブリッジ通貨としてUSDCを利用
- Web3アプリでは、CBDC残高を担保に民間コインを発行
つまり、「CBDCが信頼の根幹、ステーブルコインが流通を担う」構造が次世代の通貨システムとして現実味を帯びてきています。
まとめ|国家と民間が作る新しい通貨秩序

CBDCとステーブルコインは、互いに補完しながら新しい通貨秩序を形づくりつつあります。国家が「信頼」と「基盤」を提供し、民間が「利便性」と「革新」をもたらす。この二つの融合が進めば、国際決済の効率化・金融包摂・新しい経済圏の形成が現実のものとなるでしょう。
デジタル円の実証と世界的なCBDC連携が進む今、通貨の概念そのものが“プログラム可能な時代”に入ったといえます。それは、単なる技術革新ではなく、「お金の未来」をめぐる新たな社会構造の始まりです。