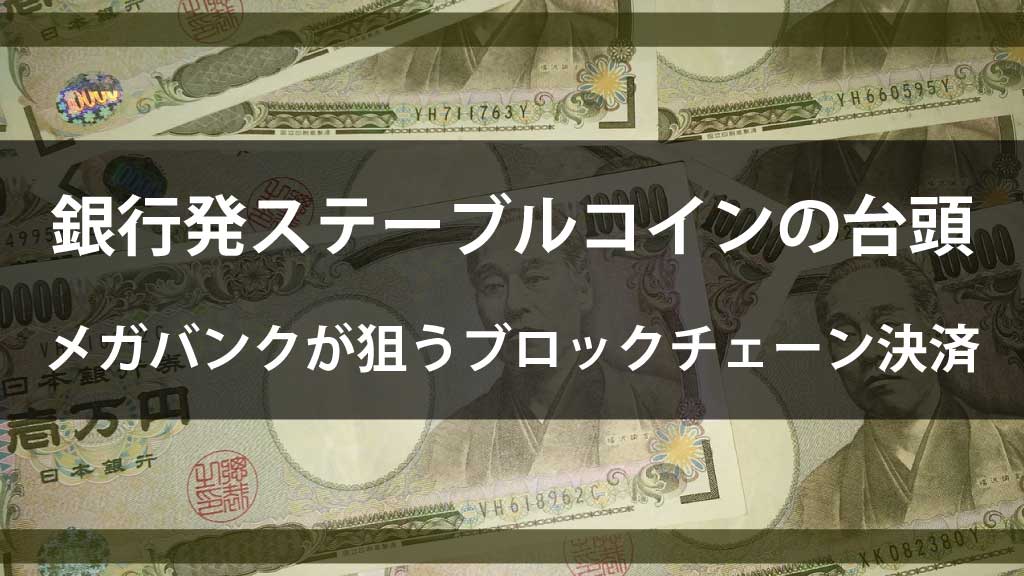はじめに|なぜ銀行がステーブルコインに参入するのか
仮想通貨は個人投資家のもの──そんな時代は過去のものになりつつあります。2025年、三菱UFJ信託銀行・みずほ・三井住友などのメガバンクが、次々とブロックチェーン型ステーブルコインを立ち上げています。背景には、決済・送金・証券取引といった既存インフラの限界と、金融機関自身のデジタルシフトがあります。
背景にあるのは、国際送金・企業間決済の非効率性です。既存の銀行ネットワーク(SWIFTなど)は安全性が高い一方で、手数料や決済時間の面で限界を抱えていました。ステーブルコインを利用すれば、リアルタイム決済・低コスト・高い透明性を同時に実現できる――。これが銀行参入の最大の理由です。
これらを解決する鍵は、官民連携によるガイドライン整備と、金融庁・日銀・ブロックチェーン事業者の協働体制です。日本が安全かつ透明なデジタル通貨インフラを構築できるかどうかは、今後数年が正念場となります。
メガバンクが動く背景|ブロックチェーン決済の「効率」と「透明性」
ブロックチェーン技術の導入によって、銀行は従来の勘定系システムでは不可能だった「瞬時決済」を実現できます。特に、スマートコントラクト(自動契約実行プログラム)の導入により、取引条件を満たした瞬間に資金を自動移転できるようになります。
この仕組みは、たとえば貿易や証券決済など、複雑な手続を伴う取引において決済リスクと事務コストを大幅に削減します。さらに、取引履歴がブロックチェーン上で改ざん不可能な形で残るため、監査コストの削減や不正防止にも寄与します。
加えて、ブロックチェーンを利用した決済は「24時間365日」「国境を越えて」「即時」で動くため、次世代の銀行間ネットワークとしての期待も高まっています。
主要プロジェクトの比較|Progmat Coin・DCJPY・デジタル通貨構想
メガバンクのステーブルコイン戦略は、単一の通貨ではなく、複数の実証プロジェクトに分かれて進行しています。以下の3つが代表的なケースです。
| プロジェクト名 | 主導銀行 | 発行方式 | 主な用途 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| Progmat Coin | 三菱UFJ信託銀行 | 信託型(資金は信託財産で保全) | 証券決済・企業間送金・NFT決済 | 金融庁登録済。民間ステーブルコインの基準モデル。 |
| DCJPY | 三井住友銀行・みずほ銀行 | 共通プラットフォーム型 | 企業間決済・貿易・エネルギー取引 | 業界横断ネットワーク。API連携で他システムと接続可能。 |
| デジタル通貨プラットフォーム構想 | みずほ銀行・デジタル庁 | 準CBDC型 | 公共料金・税支払い・自治体決済 | 公的利用を想定した次世代型。CBDC実験にも接続可能。 |
これらは競合というよりも、用途別に最適化されたステーブルコイン群と考えられています。つまり「民間×信託(Progmat)」「企業間×共通基盤(DCJPY)」「公的×行政(デジタル通貨構想)」の3層構造です。
Progmat Coinの戦略|信託を活かした“安全性の極み”モデル
Progmat Coinは、三菱UFJ信託銀行が主導する日本初の「信託型ステーブルコイン」です。利用者が保有するトークン残高に応じて、同額の日本円を信託財産として別口座で保全し、銀行破綻などのリスクを完全に遮断します。
これは海外のUSDT(テザー)やUSDCのような「準備金公開ベース」とは異なり、日本の信託法に基づいた法的保護がある点が最大の特徴です。金融庁もこのモデルを「安全な電子決済手段の典型例」として位置づけており、他行の参考基準となっています。
2025年時点では、証券会社や不動産企業との実証実験を通じて、STO(セキュリティトークン)決済や不動産取引の即時精算に活用されつつあります。Progmat Coinは単なる決済手段ではなく、ブロックチェーン版“銀行預金”とも呼ばれる存在に進化しています。
DCJPYの展開|企業間取引の標準通貨を目指して
DCJPYは、NTTデータとメガバンク連合(みずほ・三井住友など)が主導する「共通決済通貨」プロジェクトです。この構想の目的は、異なる企業間での資金移動を、共通のブロックチェーン基盤上で自動化・可視化することにあります。
貿易・エネルギー・物流・不動産など、複数業界の大企業が参加しており、実際の商取引での利用を前提とした設計です。たとえば、貿易において「商品引き渡し完了」イベントがスマートコントラクト上で検知されると、DCJPYで自動的に代金が支払われるといった仕組みが想定されています。
さらに、DCJPYはProgmatと異なり複数銀行が共通で利用可能なインフラを目指しています。このため、将来的には国内全銀行がDCJPYネットワークを通じて相互送金できる構想もあり、「B2B決済の国内標準」になる可能性を秘めています。
銀行が狙う「次のビジネスモデル」|データ駆動型金融の幕開け
銀行がステーブルコインを発行する目的は、単に手数料収入を得るためではありません。むしろ注目すべきは、ブロックチェーン上のトランザクションデータを活用したデータ駆動型金融モデルへの転換です。
ステーブルコインで処理された取引データは、従来の銀行決済では得られなかった「リアルタイムの資金フロー情報」として分析可能です。これにより、銀行は企業の信用状態を瞬時に把握し、動的な与信判断や自動融資(スマートローン)を実現できるようになります。
また、決済データをもとにした新しい収益源として、決済連動型保険・データマーケット・BaaS(Banking as a Service)などのサービス展開も進んでいます。つまり、銀行は「預金で稼ぐ」時代から、「データで価値を創る」時代へと進化しているのです。
課題と今後の展望|信頼とスピードの両立へ

とはいえ、銀行発ステーブルコインにも課題は残されています。主なものは以下の通りです。
- 異なる銀行間ネットワーク(Progmat/DCJPY)の連携未整備
- スマートコントラクトに関する法的責任の曖昧さ
- 個人情報保護とAML/KYC(本人確認)の両立
- 障害時の代替決済ルート・バックアップ体制の不足
こうした課題に対し、金融庁・日銀・デジタル庁は共同で「デジタル通貨連携基盤(DC-Platform)」の検討を開始しています。民間・公的双方が共通インフラ上でデータ連携できる仕組みが整えば、2026年以降、ステーブルコインは日常決済にも広がると予想されます。
2025年は、まさに銀行がデジタル金融の“主役”として再定義される転換点です。信頼・スピード・透明性を兼ね備えた日本型ステーブルコインが、世界市場でどう評価されるかに注目が集まります。