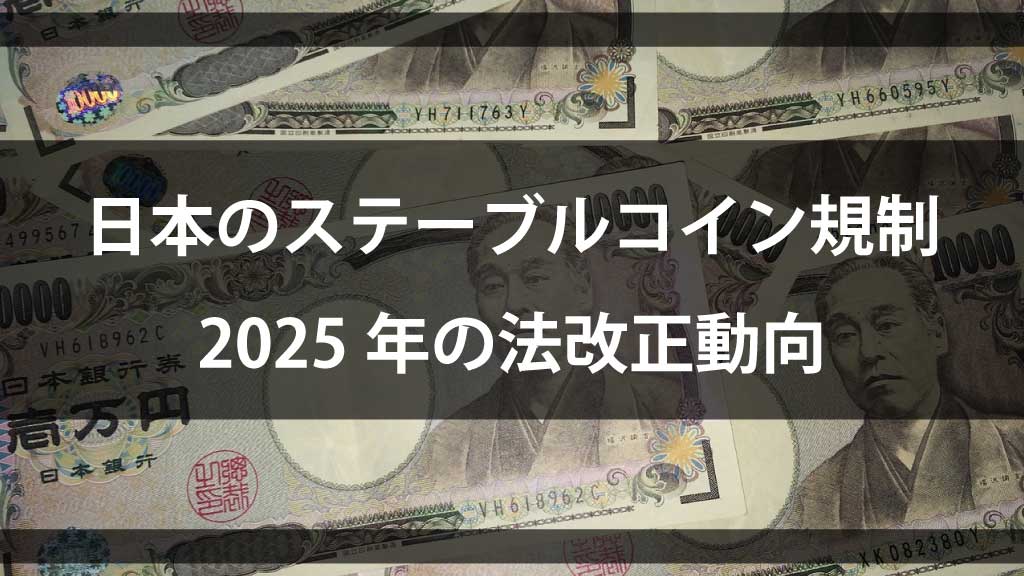はじめに|ステーブルコインを取り巻く新しい潮流
ステーブルコインは、価格の安定を目的として法定通貨などに連動する暗号資産です。これまで日本では、法的な位置づけが不明確なまま海外取引所を中心に利用されてきましたが、2023年施行の改正資金決済法により、制度として正式に整備されました。
そして2025年、ステーブルコインは「電子決済手段」として実社会での活用フェーズに入りつつあります。
日本におけるステーブルコインの法的位置づけ
改正資金決済法(2023年施行)では、ステーブルコインを「電子決済手段」として明確に定義しました。これにより、発行・管理・流通のそれぞれに法的責任が発生し、次の3種類のプレイヤーが登場しています。
① 発行者(電子決済手段発行者)|信頼の基盤を担う存在
ステーブルコインの「発行者」は、最も厳格な法的責任を負う主体です。日本では、銀行、信託会社、資金移動業者など、法定通貨を裏付けとして安全に保管できる機関のみが発行を認められています。発行者は利用者から預かった日本円などを信託口座で分別管理し、1コイン=1円を保証します。
この仕組みにより、海外のUSDTやUSDCのような「実際の裏付けが不透明なコイン」とは異なり、発行体の破綻リスクや価格乖離のリスクを最小化しています。また、金融庁の監督下に置かれ、監査報告や資産保全状況の定期的開示が義務付けられています。
代表例としては、三菱UFJ信託銀行の「Progmat Coin」や、デジタル通貨フォーラムの「DCJPY」構想などがあり、いずれも発行者が実際の日本円を保管し、その裏付けとしてトークンを発行しています。
② 電子決済手段取引業者|発行と利用をつなぐ中間事業者
電子決済手段取引業者(Electronic Payment Instruments Service Provider)は、発行されたステーブルコインを一般利用者や企業が取引・送金できるようにする仲介者です。仮想通貨交換業者と似ていますが、異なる法的枠組みで規定されています。
取引業者は、利用者登録(KYC)、本人確認・AML対策、トランザクション記録の保管といった厳格な管理義務を負います。特に2025年以降は、海外発行ステーブルコイン(USDT・USDCなど)を扱う場合、国内登録済み取引業者を経由しなければ販売できないという制限が強化されています。
これはマネーロンダリング防止の観点から重要であり、「国内の信頼あるゲートウェイ」として機能する役割が求められています。将来的には、証券会社・フィンテック企業・大手決済アプリなどがこの区分に参入することが予想されています。
③ 情報通信事業者(技術提供者)|ブロックチェーン基盤を支える裏方
情報通信事業者は、ステーブルコインの「ブロックチェーン上での発行・送金・記録」を技術的に支える存在です。このカテゴリーには、ブロックチェーン開発企業・ネットワーク運営者・API提供者などが含まれます。
彼らは直接コインを発行するわけではありませんが、信頼性・可用性・セキュリティの観点から重要な責任を負います。特に日本では、システム障害時の取引記録の改ざん防止・バックアップ体制などが求められており、単なる「技術提供」にとどまらない位置づけです。
具体例として、Progmat(MUFGグループ)では独自ブロックチェーン基盤を、DCJPYではNTTデータが共同開発を担当しています。このように、金融機関とIT事業者の協働こそが日本型ステーブルコインの特徴といえるでしょう。
従来の「暗号資産交換業者」と異なり、これらのプレイヤーは金融庁への登録と厳格な資産保全義務を負います。この点が、海外の無担保型ステーブルコイン(例:USDT、USDC)との最大の違いです。
2025年の最新法改正・金融庁ガイドラインの要点
2023年の改正資金決済法施行後、日本ではステーブルコイン制度の実運用が段階的に進んできました。2025年は、その中で制度の実効性を高めるための「第2段階」と位置づけられています。金融庁は2024年末に「電子決済手段に関する監督指針」を改訂し、次の3点を重点方針として打ち出しました。
1. 電子決済手段発行者の内部統制・監査体制の厳格化
発行者は、顧客資産の管理・運用において第三者監査・内部統制報告を義務づけられます。特に「信託財産の管理方法」「トークン発行・償還手続」「資金移動業者との連携リスク」など、従来はガイドラインレベルに留まっていた項目が、監督対象に明示されました。
これにより、実際にステーブルコインを発行する銀行や信託会社は、従来の決済業務に加え、ブロックチェーン監査・スマートコントラクト監視といった新しい管理領域に対応する必要があります。
2. 海外発行ステーブルコインの国内流通ルールの明確化
これまでグレーゾーンだった「USDT」「USDC」などの海外発行コインについて、2025年からは次のようなルールが明文化されています。
- 国内登録業者を通じてのみ取引が可能(個人輸入的な直接送金は禁止)
- 裏付け資産・準備金情報の日本語での定期開示を義務化
- 為替変動リスク・価格乖離に関する利用者説明文書の提示を義務化
この規制強化により、無登録業者を介したステーブルコイン取引は違法リスクを伴うようになり、信頼性のある事業者による健全な市場形成が進むことが期待されています。
3. 実需利用促進のための上限緩和と相互運用性の検討
商取引や給与支払いなど、法人利用を見据えた制度緩和も始まっています。従来は1取引あたり100万円以下などの制限が設けられていましたが、2025年改訂で法人間取引に限り上限が緩和されました。
また、金融庁・経産省・日銀の合同検討会では、CBDC(中央銀行デジタル通貨)との相互運用も視野に入れた制度設計が議論されています。「Progmat」「DCJPY」「JPYC」など、民間プロジェクトとのAPI連携・インターフェース共通化が進められており、2026年以降に実証フェーズへ移行する見込みです。
国内主要プロジェクトの動向

日本円建てステーブルコインの実用化は、2024〜2025年にかけて大きく前進しています。特に注目されるのは、三菱UFJ信託銀行の「Progmat Coin」、デジタル通貨フォーラム(DCJPY)、そして民間発行型の「JPYC」です。
① Progmat Coin(プログマ・コイン)|銀行信託モデルの代表格
発行主体: 三菱UFJ信託銀行
特長: 信託財産を裏付け資産とする「信託型ステーブルコイン」。金融庁登録済。
Progmatは、MUFGが主導するブロックチェーン基盤「Progmat Network」を使用し、円・ドル・ユーロ建てトークンの発行にも対応できる構造を備えています。
2025年には、地方銀行・証券会社・フィンテック企業との連携が進み、証券決済・企業間送金・NFT決済など、幅広い用途での実証が開始されています。特に、Progmat Coinは「CBDCに最も近い民間通貨」として注目されており、金融庁のモデルケースとされています。
② JPYC|民間発行型ステーブルコインの先駆け
発行主体: 株式会社JPYC
特長: 事前チャージ方式(プリペイド)で1JPYC=1円として利用可能。JPYCは電子マネー法に準拠し、資金移動業者として登録済み。Ethereum、Polygon、Avalancheなど複数チェーンに対応しています。
2024〜2025年にかけては、Visa・Mastercard連携のデビット決済、NFTマーケット支払い、地方自治体のデジタル地域通貨実験にも参加。政府方針の「デジタル給与支払い解禁」により、給与トークンとしての利用実験も始まっています。
③ DCJPY(デジタル通貨フォーラム)|企業間決済の実証モデル
運営主体: デジタル通貨フォーラム(事務局:NTTデータ)
参加企業: 三井住友銀行、みずほ銀行、NTTグループ、電力・物流・航空各社など約100社。DCJPYは、企業間取引に特化したステーブルコイン構想であり、Progmatとは異なり「共通プラットフォーム」での利用を前提としています。
2025年には、貿易決済・エネルギー取引・不動産登記支払いなど複数分野での実証実験を実施中。特にブロックチェーン間の相互運用性(Interoperability)を重視しており、将来的にはCBDCや海外通貨トークンとの連携も検討されています。
④ 地方銀行・自治体による地域ステーブルコイン構想
近年は、地方自治体や地方銀行が主導する「地域通貨型ステーブルコイン」も登場しています。例として、長野県・静岡県では観光促進を目的に、ブロックチェーン上で発行される地域トークンを実証中。
これらはJPYCなど既存コインを基盤にするケースも多く、「地域金融×ブロックチェーン」の融合が加速しています。
まとめ:日本型ステーブルコインの特徴
- 信託・銀行ベースの高い信頼性
- 法定通貨1:1の完全裏付け構造
- 金融庁監督下での透明な運用体制
- CBDCとの連携を視野に入れた中長期ロードマップ
これらの取り組みが進むことで、ステーブルコインは「投機対象」から「社会インフラ」へと進化しつつあります。2025年は、まさに日本がデジタル通貨の実用化フェーズに入る転換点といえるでしょう。
今後の市場影響と課題
日本におけるステーブルコイン制度化は、金融のデジタル化を推進する重要な一歩です。一方で、課題も少なくありません。
- 銀行・信託会社以外の参入ハードルが高い
- AML/KYC対応コストの上昇
- 海外発行コイン(USDTなど)との相互運用性の課題
これらを克服するためには、官民連携による実証実験の継続と、利用者側への教育・理解促進が不可欠です。
まとめ|ステーブルコインの未来は「信頼性」と「実用性」へ
2025年の日本では、ステーブルコインが単なる投機対象から「社会インフラ」へと進化を遂げようとしています。
制度・技術・金融の三位一体による新たな決済の形が、数年内に一般化する可能性も高まっています。
今後は、各企業や自治体がどのように「円建てデジタル通貨」を活用していくかに注目が集まるでしょう。